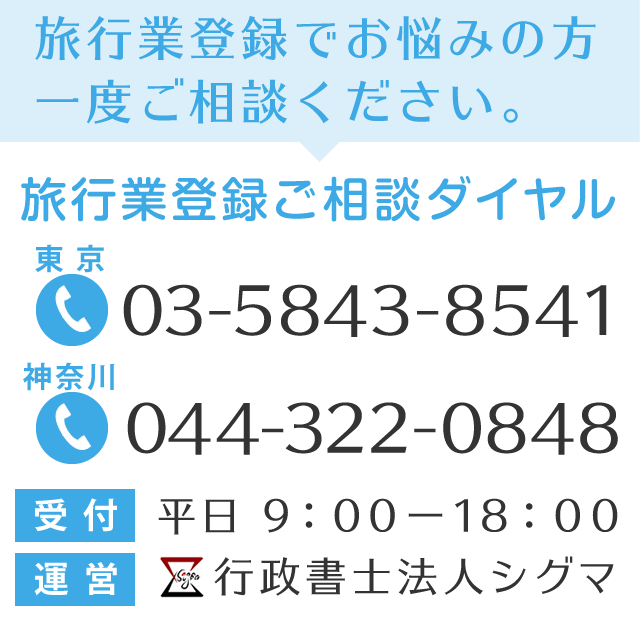インバウンド需要の回復や、新たな観光スタイルへの関心の高まりを受け、旅行関連ビジネスへの注目が集まっています。しかし、「旅行会社」や「旅行代理店」と呼ばれる事業を始めるには、旅行業法に基づいた営業許可申請手続きが必要になります。そこで今回は、旅行業の許認可法務に関するエキスパートである行政書士法人シグマの代表行政書士である阪本浩毅さんをお招きし、複雑で分かりにくい「旅行業登録」の全体像について、詳しくお話を伺いました。
旅行業を始めるための第一歩「旅行業登録」とは
──本日はお忙しい中ありがとうございます。早速ですが、旅行会社や旅行代理店を経営するために必要となる「旅行業登録」とは、そもそもどのような制度なのでしょうか?
阪本:はい。旅行業を営むためには、旅行業法という法律に基づいて、行政庁に「旅行業を行います」という登録をしなければなりません。これが「旅行業登録」です。この登録を受けることで、初めて正式に旅行ビジネスをスタートできる、いわば営業免許、営業ライセンスのようなものですね。
──なるほど、事業のライセンスですか。その根拠となる「旅行業法」というのは、どういった目的の法律なのでしょう?
阪本:旅行業法は、旅行業を営む事業者を規制するための法律ですが、旅行業を規制しているのは「旅行者の保護」のためです。旅行商品はツアーや航空券といった形のない「無形商品」にもかかわらず、高額な代金を前払いすることも少なくありませんよね。
──確かに、支払ったのに手配されていなかった、といったトラブルを聞くことがあります。
阪本:その通りです。そうした消費者トラブルを防ぐため、法律で事業者に一定のルールを課しているのです。例えば、不適切な事業者を排除するための登録制度を設けたり、契約内容の十分な説明や、旅行中の安全管理などを義務付けたりすることで、旅行者が安心・安全の旅行を楽しめる環境を整えています。
──ちなみに、法律では私たちのことを「旅行者」と呼ぶんですね。なんだか旅の途中という感じがします。
阪本:そうなんです。面白いですよね。法律上の「旅行者」とは、実際に旅行中の方だけでなく、これから旅行の申し込みをしようとしているお客様も含まれる、非常に広い概念で使われています。
そのビジネス、本当に「旅行業」?登録が必要な業務の範囲
──では、具体的にどのような業務を行う場合に、この旅行業登録が必要になるのでしょうか?
阪本:はい、ここが非常に重要なポイントです。「報酬を得て、事業として」行う特定の行為が旅行業にあたります。大きく分けると4つの行為に分類できます。
──4つの行為、ですか。ぜひ詳しく教えてください。
阪本:まず一つ目は、旅行会社がオリジナルのツアーを企画して実施する「企画旅行」に関する行為です。パンフレットなどで参加者を募る「募集型」と、お客様の要望に応じてオーダーメイドで計画を立てる「受注型」がありますが、どちらも運送や宿泊サービスなどを仕入れて手配する行為が該当します。
──いわゆるパッケージツアーのようなイメージですね。二つ目は何でしょうか?
阪本:二つ目は「手配旅行」に関する行為です。これは、お客様の依頼に応じて、航空券や新幹線の切符、ホテルの宿泊などを個別に手配する業務を指します。航空券1枚の手配から、交通と宿泊の組み合わせまで、形態は様々です。これらに付随して、レストランや観光施設のチケットを手配することも含まれます。
──なるほど。三つ目と四つ目はどのようなものでしょうか?
阪本:三つ目は、これまでお話しした旅行に付随する、ガイドや添乗といった案内サービスや、パスポート・ビザの取得代行手続きなどです。そして四つ目、これが意外に思われるかもしれませんが、「旅行相談」も報酬を得て事業として行えば旅行業にあたります。旅のプランニング自体を商品として提供するようなケースですね。
──相談するだけでも旅行業になる場合があるとは驚きです。逆に、旅行業登録が不要なケースはあるのでしょうか?
阪本:はい、あります。例えば、観光施設の入場券や観劇チケットの販売だけを行う場合や、純粋なガイド業務だけを専門に行う場合は登録不要です。これらは「運送等関連サービス」と呼ばれ、運送や宿泊の手配を伴わないため、単独であれば旅行業には該当しません。

──最近よく見る、地域の体験アクティビティを予約できるサイトなども、運送や宿泊がセットでなければ登録は要らない、という理解で合っていますか?
阪本:その通りです。非常に良い例ですね。また、バス会社の営業所の近くのお店が、そのバス会社の回数券だけを販売するようなケースも、運送機関の代理販売に特化しているため例外的に登録は不要です。さらに、バス会社自身が自社のバスで日帰りツアーを実施したり、ホテルが近隣のゴルフ場やテーマパークと組んで宿泊パックを販売したりするのも、自社サービスの範囲内と見なされ、旅行業登録は必要ありません。
──最近、「ランドオペレーター」という言葉も聞きますが、これは旅行業とは違うのですか?
阪本:良い質問ですね。ランドオペレーターは、主に海外の旅行会社などからの依頼を受けて、日本国内でのバスやホテル、ガイドなどを手配する事業者のことです。これは従来の旅行業とは異なり、「旅行サービス手配業」という別の登録が必要になります。ただし、旅行業登録を取得していれば、この手配業の登録を別途取得する必要はありません。
事業計画に合わせた登録種別の選び方
──旅行業と一言で言っても、業務範囲によって色々な形態があるのですね。登録の種類もいくつかあるのでしょうか?
阪本:はい。事業で取り扱える業務の範囲によって、大きく5つの種別に分かれています。まず、海外・国内すべての旅行業務が扱えるオールマイティな「第1種」。次に、自社での海外募集型企画旅行(パッケージツアー)の実施はできませんが、それ以外の海外・国内業務が可能な「第2種」。そして、海外募集型企画旅行の実施ができず、国内の募集型企画旅行も営業所周辺の限定的な範囲に絞られる「第3種」です。
──第1種が最も範囲が広いわけですね。残りの2つは何ですか?
阪本:最近注目されているのが「地域限定旅行業」です。これは、事業区域を特定の地域に限定して、そのエリア内での着地型観光(オプショナルツアーなど)の企画・実施に特化したものです。インバウンド需要や地方創生の観点から、この登録を目指す事業者さんが増えていますね。最後は、特定の旅行会社(親会社)の商品のみを販売する代理店である「旅行業者代理業」です。
──なるほど、自社のビジネスモデルに合わせて適切な種別を選ぶことが重要ですね。第3種や地域限定旅行業の「限定的な範囲」とは、具体的にどのくらいなのでしょうか?
阪本:これは、営業所がある市町村と、それに隣接する市町村、さらに観光庁が定める特定の地域内に、出発地から帰着地までが収まる旅行、と定義されています。例えば、特定の温泉地エリアでのみ完結する日帰り体験ツアーなどが典型例です。
登録のためにクリアすべき必須要件
──いざ登録しようとなった場合、誰でも申請できるわけではないですよね。どのような要件を満たす必要があるのでしょうか?
阪本:おっしゃる通り、登録にはいくつかの重要な要件があります。まず大前提として、申請者や法人の役員が、過去に旅行業法の違反で登録を取り消されたり、一定の刑罰を受けたりしていない、といった「欠格事由」に該当しないことが求められます。
──そして、専門知識を持つ人材も必要になりそうですね。
阪本:その通りです。各営業所に必ず1名以上、「旅行業務取扱管理者」という国家資格を持った責任者を、常勤で選任しなければなりません。この管理者は、いわば旅行取引のプロフェッショナル。お客様との公正な取引と安全を確保する上で中心的な役割を担います。海外旅行を扱う営業所では、より難易度の高い「総合旅行業務取扱管理者」の資格が必要です。
──管理者がもし退職してしまったら、どうなるのですか?これは実務上の落とし穴になりそうです。
阪本:非常に重要なご指摘です。管理者が一人もいなくなってしまった場合、後任者が選任されるまで、その営業所では旅行に関する新規契約が一切できなくなります。つまり、事業が完全にストップしてしまうのです。人材の確保と定着は、経営上の大きな課題と言えます。
──それは死活問題ですね…。他に金銭的な要件はありますか?
阪本:はい。「基準資産額」という財産的基礎の要件があります。これは旅行業のみに課されるもので、万が一の際に旅行者への弁済能力を担保するためのものです。種別ごとに額が異なり、第1種で3,000万円、第2種で700万円、第3種で300万円、地域限定旅行業で100万円以上が必要となります。
──その「基準資産額」というのは、会社の資本金のこととは違うのですね?
阪本:違います。よくある誤解なのですが、これは会社の資産総額から負債や営業保証金などを差し引いた、いわば「正味の財産」のことです。設立したばかりの会社であれば設立時の貸借対照表で、既存の会社なら直近の決算書でこの額を証明する必要があります。資本金が300万円あっても、借入金が多ければ基準資産額を満たせない、というケースも十分にあり得ます。
登録手続きの流れと費用について
──要件を満たしたら、いよいよ申請手続きですね。どのような流れで進むのでしょうか?
阪本:まず、登録行政庁がどこになるかを確認します。第1種旅行業は国の観光庁ですが、第2種以下は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事になります。例えば、本社が神奈川県にあっても、メインで営業するオフィスが東京都にあれば、申請先は東京都です。その後、申請書類を作成し、行政庁の担当者とのヒアリングを経て申請受理、審査という流れが一般的です。無事に登録通知書が届いたら、登録免許税や手数料を納付し、後述する営業保証金を供託、もしくは旅行業協会へ分担金を納付して、ようやく営業開始となります。
──申請から営業開始まで、どれくらいの期間を見ておけば良いでしょうか?
阪本:これは行政庁によって大きく異なりますが、例えば東京都で第2種や第3種の登録をする場合、ご相談いただいてから営業開始まで、おおよそ2.5ヶ月が標準的な期間です。第1種の場合は観光庁と運輸局の両方が関わるため、4ヶ月程度かかることもあります。

──費用面も気になります。申請手数料の他に、先ほど出た「営業保証金」とは何でしょうか?
阪本:営業保証金は、万が一会社が倒産するなどして旅行代金の返済ができなくなった場合に備え、あらかじめ国(法務局)に預けておくお金です。これも種別や年間の取引額によって変動しますが、例えば第2種だと最低でも1,100万円、第3種でも300万円と、かなり高額になります。
──それは、特にスタートアップにとっては大きな負担ですね。
阪本:はい。そこで多くの事業者が利用するのが「旅行業協会」への加入です。日本旅行業協会(JATA)か全国旅行業協会(ANTA)のどちらかに加入して保証社員になることで、この営業保証金の供託が免除され、代わりにその5分の1の額にあたる「弁済業務保証金分担金」を協会に納付すれば済む、という制度があります。
──5分の1ですか!それは大きなメリットですね。JATAとANTA、どちらを選ぶべきか悩む方も多そうです。
阪-本:そうですね。受けられる基本的なサービスはほぼ同じですが、費用面ではANTAの方が安価な傾向にあります。一方、JATAは入会手続きがスピーディーなため、一日でも早く営業を開始したいという方が選ばれることが多いです。また、JATAは海外旅行に強い大手、ANTAは国内旅行中心の中小事業者が多いというカラーの違いもありますので、自社の事業内容や将来的なネットワーク作りを考えて選ぶのも良いでしょう。
専門家からのアドバイス:失敗しないための準備とは
──登録後も、5年ごとの更新や毎年の取引額報告など、様々な手続きが必要なのですね。
阪本:その通りです。特に5年後の更新時に、基準資産額を満たせなくなってしまうケースは少なくありません。日々の経営はもちろん、財務状況の管理が非常に重要になります。
──最後に、これから旅行業を始めようと考えている方々へ、専門家としてアドバイスをお願いします。
阪本:最もお伝えしたいのは、「できるだけ早い段階で、専門家に相談してほしい」ということです。特に、これから会社を設立して旅行業を始めるのであれば、会社設立の「前」にご相談いただくのがベストです。
──設立後では遅いのでしょうか?
阪本:遅い、というより、遠回りになってしまう可能性があります。実際にあったケースですが、会社設立後にご相談に来られたところ、定款の事業目的に「旅行業」の文言が入っていなかったり、資本金が基準資産額の要件を考慮していない額だったりして、再度、定款変更や増資の登記手続きが必要になってしまったのです。これでは余計な時間と費用がかかってしまい、非常にもったいないですよね。
──会社設立のプロである司法書士さんに依頼しても、そうしたことが起こり得るのですね。
阪本:はい。司法書士さんは登記の専門家ですが、旅行業登録の専門家ではありません。それぞれの許認可には、その法律特有の細かな要件があるのです。事業の根幹となる許認可ですから、ぜひ旅行業に精通した行政書士を見つけて、二人三脚で準備を進めることをお勧めします。スムーズなスタートアップが、その後の事業の成功にも繋がっていくはずです。
──事業計画の段階から専門家を巻き込むことが、成功への近道なのですね。本日は大変勉強になりました。ありがとうございました。

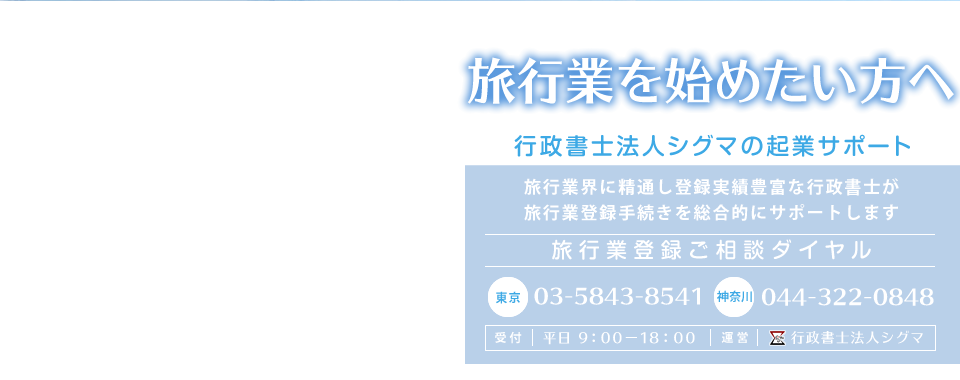
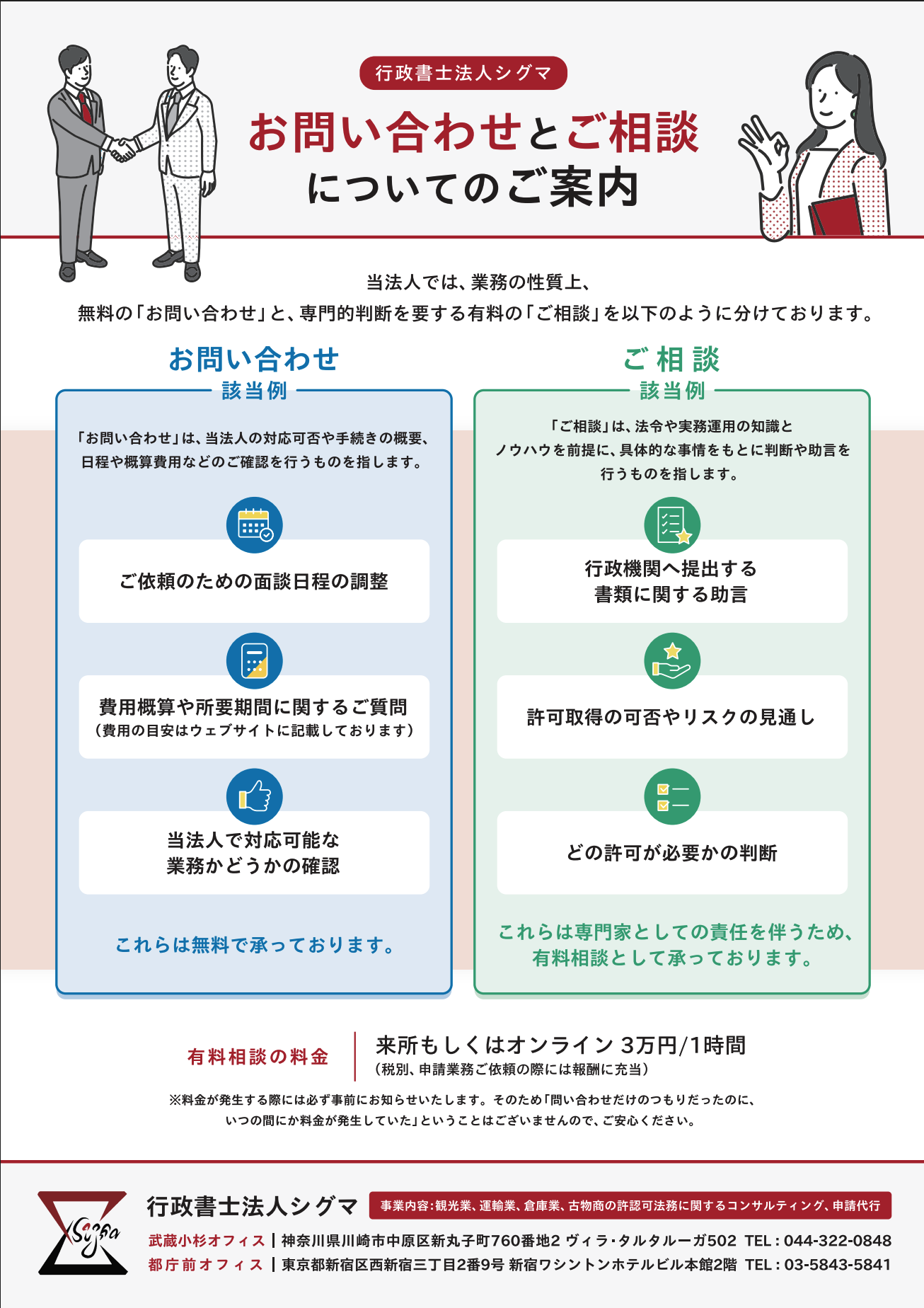
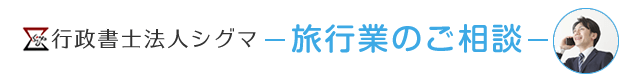
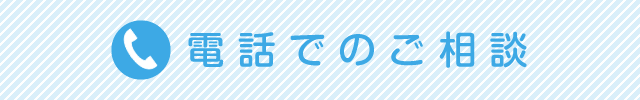

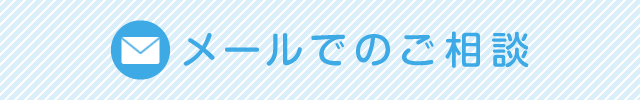
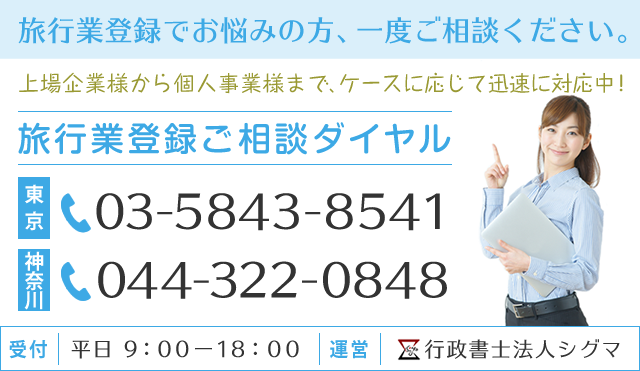
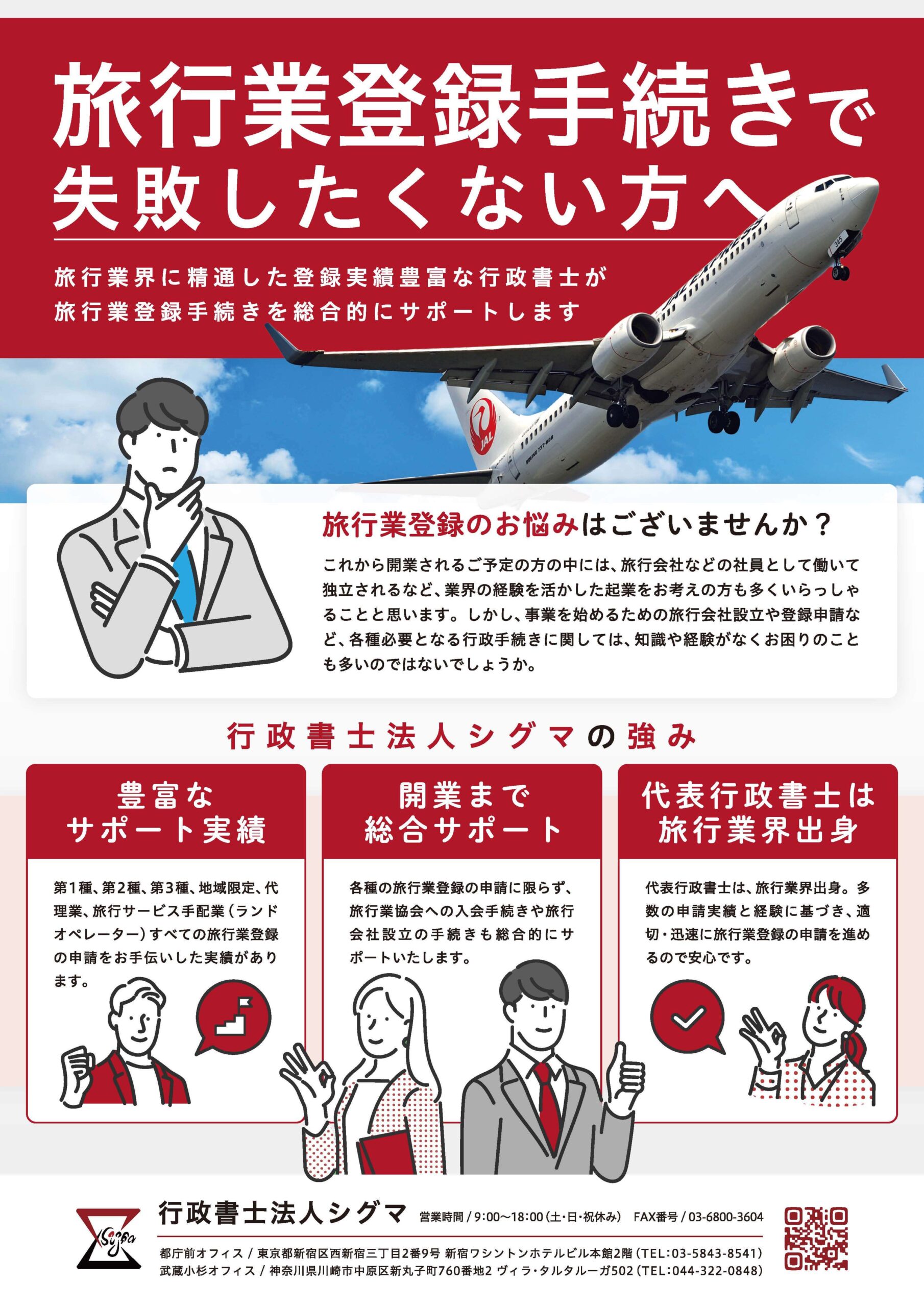

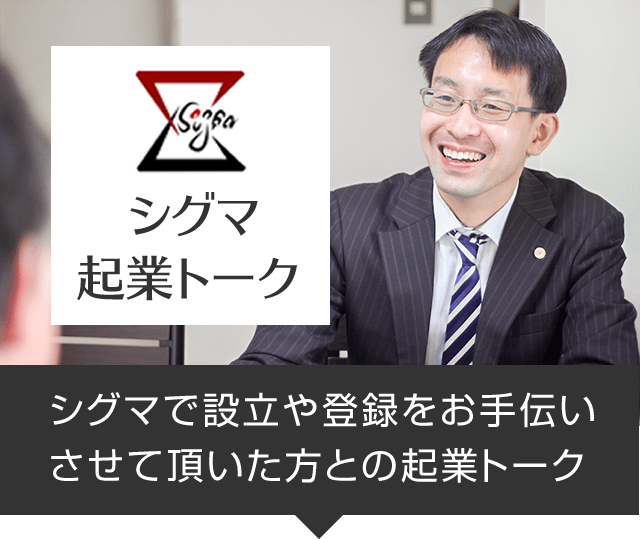
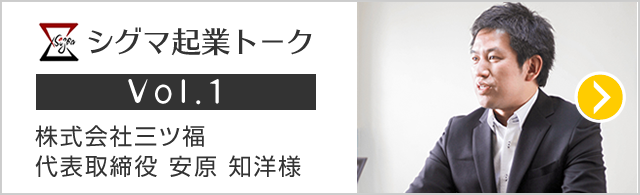
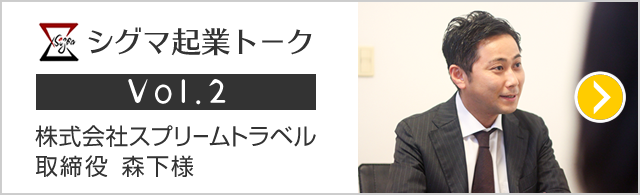
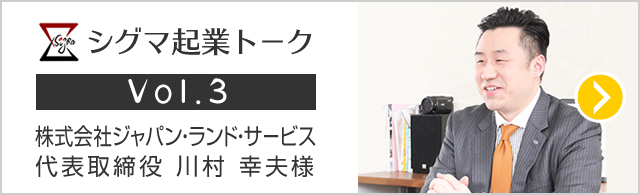

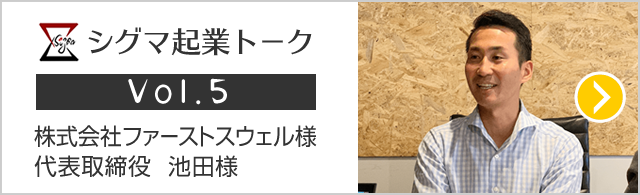
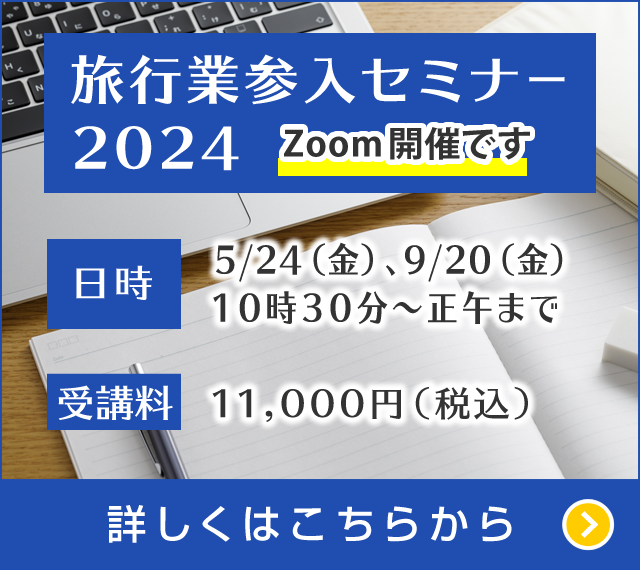
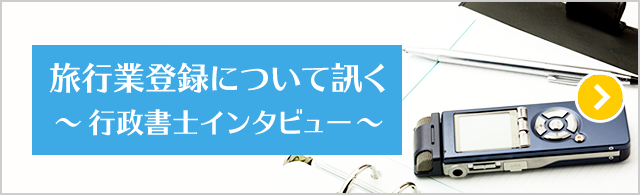




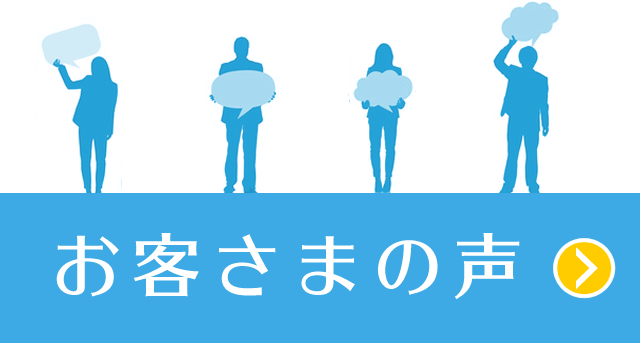


 国土交通省
国土交通省
 関東運輸局
関東運輸局
 東京都庁
東京都庁